認知症の種類と症状について
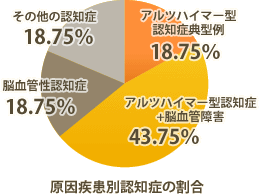 認知症は、かつては“痴呆””痴呆症”などと呼ばれていましたが、平成16年に厚生労働省によって用語検討が行われ、新たに”認知症”と呼ばれるようになりました。認知症とは、医学的には「知能が後天的に低下した状態」とされています。もともと健常であった脳が、脳血管疾患やアルツハイマー病といった病気が原因でその働きが悪くなり、物忘れや妄想、幻覚、人格崩壊といった症状を引き起こす状態。単に老化によって物覚えが悪くなるといった現象は、認知症には含まないのです。
認知症は、かつては“痴呆””痴呆症”などと呼ばれていましたが、平成16年に厚生労働省によって用語検討が行われ、新たに”認知症”と呼ばれるようになりました。認知症とは、医学的には「知能が後天的に低下した状態」とされています。もともと健常であった脳が、脳血管疾患やアルツハイマー病といった病気が原因でその働きが悪くなり、物忘れや妄想、幻覚、人格崩壊といった症状を引き起こす状態。単に老化によって物覚えが悪くなるといった現象は、認知症には含まないのです。
日本では昔から、血管性認知症が最も多かったのですが、昨今ではアルツハイマー型認知症が増えてきており、認知症の中ではこの2種類が多いタイプとなっています。
認知症の主な種類
脳血管性認知症
脳血管性認知症とは、脳梗塞や脳出血などが原因で脳内の神経組織が破壊されることによって起こる認知症です。
主な症状は、記憶障害とその他の認知機能障害(言葉、動作、認知などの障害)など。特徴としては、症状が突如として現れたり、その後になって階段状に悪化したり、または変動したりする場合があるという点です。
残念ながら、現段階では症状を改善させる確実な方法はありません。そのため、脳血管障害の再発予防と認知症の対症療法が治療の中心。高血圧や糖尿病などの持病を患っている方は、特に注意した生活を送ると良いですね。
アルツハイマー型認知症
認知症の主な原因であるアルツハイマー病は、何が原因で起こるのか、未だに解明されていません。
一般的には、脳内の神経細胞が何らかの異常により激減し、脳が委縮することが原因と言われています。
症状は、脳血管性認知症と似ています。ただし、初期症状は分かりにくく、ゆっくりと進行していくという特徴があります。
明確な治療法は確立されていませんが、認知症の対症療法や、脳内に不足している物質を投与する薬物療法が有効とされています。
認知症の主な症状
認知症の症状は、記憶障害を中心とした中核症状と、そこに本人の性格や環境の変化などが加わって起こる周辺症状があります。
中核症状
中核症状とは、脳の神経細胞の破壊によって起こる症状です。
代表的な症状は記憶障害で、特に、直前に起きたことも忘れるような症状が顕著です。その一方、古い過去の記憶はよく残りますが、症状の進行とともに、それらも失われることが多いようです。
また、筋道を立てた思考ができなくなる判断力の低下、時間や場所、名前などが分からなくなる見当識障害などがあります。
周辺症状について
周辺症状は、中核症状の文字通り“周辺”として起こる症状で、妄想を抱いたり、幻覚を見たり、暴力をふるったり、徘徊したりするといった精神症状が現れます。また同時に、うつや不安感、無気力といった感情障害が起こるケースもあります。
周辺症状はその人の性格や環境、人間関係などが絡み合って起きるものです。そのため、症状は人それぞれ異なり、また接する人や日時によっても大きく変わってきます。
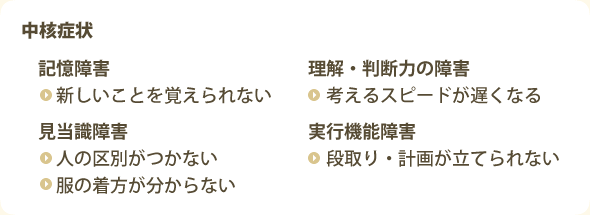

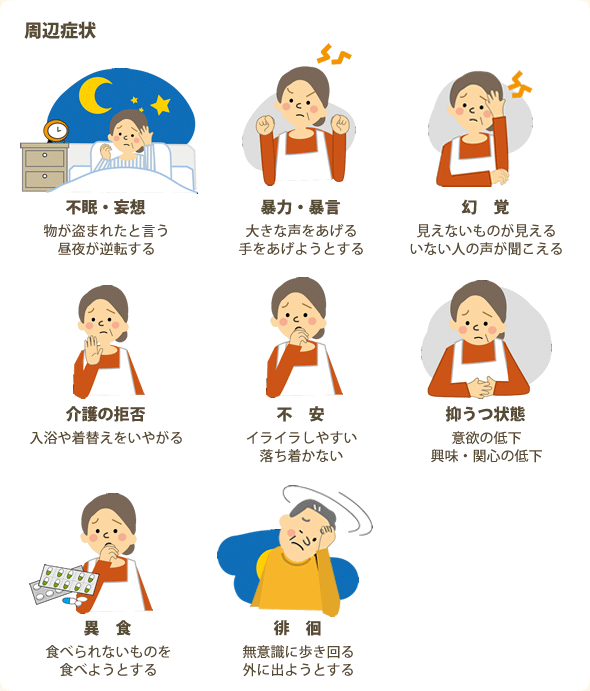
認知症患者への対応
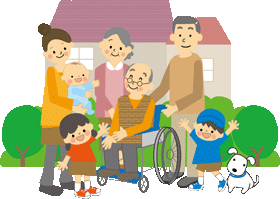 最近の研究では、脳が学習や創造、記憶などの刺激を受けることで、脳内の神経細胞が再生することが分かってきました。認知症の進行を防ぐには、人と接したり、定期的に屋外へ出掛けたりといった適度な運動をすることで、脳に刺激を与えることが重要となります。また他にも、刺激を与えて脳を活性化させる回想法や音楽療法、芸術療法といった治療法が、実際に医療機関などで実践されています。
最近の研究では、脳が学習や創造、記憶などの刺激を受けることで、脳内の神経細胞が再生することが分かってきました。認知症の進行を防ぐには、人と接したり、定期的に屋外へ出掛けたりといった適度な運動をすることで、脳に刺激を与えることが重要となります。また他にも、刺激を与えて脳を活性化させる回想法や音楽療法、芸術療法といった治療法が、実際に医療機関などで実践されています。
自宅でできる認知症の進行防止策としては、カロリーの摂取を控えるといった食事制限が重要と言われています。脳血管疾患の場合、特に高血圧や糖尿病を患っている方は、再発防止のために食事療法は有効とされています。かかりつけの医者と相談し、認知症の症状に合わせた適切な対応をとりましょう。
認知症の方を在宅で介護をする場合には、相手の気持ちを思いやり、相手の生活しやすい環境作りを整えることが重要となります。認知症の方の介護やお世話は確かに簡単なものではありませんが、少しの思いやりをもって接することでお互いが気持ち良く生活することができるはず。以下の点に気をつけて、日々を過ごしてみてはいかがでしょうか?
- 叱らない、説得しないこと
- 同じ失敗をしない様に環境を整える
- 話題を変え、関心をそらせる
- 認知症の方の認識に合わせる
認知症介護のポイント
 高齢者の気持ちを第一に考え、傷付けたり負担に思わせたりしないような配慮をすることが大事です。いろいろな接し方を試してみて上手くいった方法が、そのご家庭にとっての正しい方法だと言えるでしょう。
高齢者の気持ちを第一に考え、傷付けたり負担に思わせたりしないような配慮をすることが大事です。いろいろな接し方を試してみて上手くいった方法が、そのご家庭にとっての正しい方法だと言えるでしょう。


よろしくお願いいたします